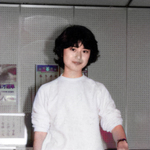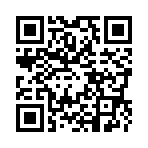2020年03月01日
聡明な人でさえ、成功し続けるのが難しい
面白い話が載っていました。「なぜ多くの優れた企業が失敗するのでしょう?」という話です。
クレイトン・クリステンセン教授は、ハーバード・ビジネス・スクールの博士課程のあるセミナーで学生たちに問いかけました。クラスにはビジネススクールの教授を目指す数十人の新入生がいました。当時のクラス生徒は世間知らずで、実際のビジネスについてはほとんど何もわかっていませんでした。
「わたしが知りたいのは、無敵だと思われていた企業のほとんどが、10年から20年後には、業界の中位または下位に転落するのはなぜなのか、ということです。わたしは大企業のCEOを何人も知っていますが、彼らの聡明さは衰えを知りません。企業の業績が絶好調である間は彼らの知性が称賛されますが、業績が悪化すると愚かさを批判されます。しかし、わたしは人間の知性の振れ幅がそれほど大きいとは思えないのです」
「そこで問うべきは……」
クリステンセン教授は黒板を見つめ、チョークを拾い上げて続けました。
「それほど聡明な人でさえ、成功し続けるのが難しいのはなぜなのか?」
これこそがまさに「イノベーションのジレンマ」でした。つまり、「正しく行う」ことが失敗を招くのです。
クリステンセン教授の『イノベーションのジレンマ』が出版されたのは1997年。それから20年以上が経過した、今でも多くの大企業は「正しく行う」ことに躍起になっています。
顧客の声に耳を傾け、より多くのより良い製品を提供するために、新しいテクノロジーに積極的に投資し、慎重に市場動向を分析し、最良のリターンが得られそうなイノベーションに計画的に出資する――皮肉なことに、これらすべてを正しく行っているがゆえに、優良企業はディスラプション(破壊)をもたらす新興企業にとって代わられるのです。
クリステンセン教授の時代、こうした転落を経験した企業に、ソニーに負けたRCA(RCAレコード)がありました。DEC(ディジタル・イクイップメント・コーポレーション)に苦しめられたNCRがありました。サンディスクに苦しめられたシーゲート・テクノロジーがありました。さらに、ホンダと戦ったハーレーダビッドソンも。
現在このパターンは、アマゾン対ウォルマート、ハリーズ対ジレット、テスラ対BMW、リボルート対HSBC、およびベターメント対メリルリンチなどと置き換えられます。役者は入れ替わりつつ、同じ物語が続いているのです。
RCAがソニーにやられた物語を振り返ってみましょう。

RCAがトランジスタ技術をはじめて発見したとき、同社はすでに真空管のカラーテレビで大成功していました。同社はトランジスタをちょっと面白い新技術というくらいの認識で実用化は考えず、ソニーというほとんど無名の日本企業にこの技術のライセンスを供与しました。
ソニーはすぐにはトランジスタテレビを作ることはできませんでしたが、世界初のトランジスタラジオを製造することに成功しました。音質は酷いものでしたが、ティーンエイジャーたちは親にがみがみ言われることなくロックを自由に聴くことができるとこのラジオに熱狂しました。そこからトランジスタラジオは広まっていきました。しかし利益率が非常に低かったので、RCAはこの技術にさらに投資する理由がありませんでした。RCAは研究開発費のすべてを稼ぎ頭の真空管カラーテレビの改善のために投入したのです。
一方、ソニーはトランジスタ技術を使った次の大ヒット商品を探していました。そして、低所得層向けに格安のポータブル白黒テレビを発売しました。Tummy Televisionと呼ばれるこのテレビは、お腹の上にのるほど小さいもので、これは中産階級のリビングルーム向けに設計されたRCAの大型テレビの向こうを張ったものでした。当時、RCAがトランジスタ技術に投資して、性能も低いテレビをそれほど魅力的のない市場に投入するなど考えられないことでした。
ソニーは一歩一歩着実にトランジスタの性能を改善していき、世界初のオールトランジスタカラーテレビを発売しました。自分たちが開発した技術をライセンス供与してから30年がたっていました。下級技術と思われていたものが後にとてつもなく有用性が高いものになったわけです。クリステンセン教授はこれをディスラプティブ(破壊的)な技術と呼びました。その後、この言葉はビジネス用語として定着し、シリコンバレーのスタートアップの間で合言葉となりました。
クリステンセン教授は自分の理論を掘り下げるために多くのケースブックを書きました。業界の未来を予測し、医療、幼稚園から高校までの教育、そして高等教育の調査などを行いました。彼は国家の繁栄の原因を分析し、最終的に生命とその意味までも研究対象としました。
彼は経営陣がよい判断ができるようにと彼の理論を実践するためのコンサルティング会社Innosightを設立しました。ハーバード・ビジネス・スクールで最も人気のあるMBAのクラスを教えながら、彼はベンチャー企業に種をまき、ディスラプティブな可能性のあるスタートアップに投資しました。
クリステンセン教授の別の授業で、彼がインテルのCEOだったアンディ・グローブと最初に会った時の話も聴きました。彼らの邂逅は、『イノベーションのジレンマ』が出版されるずっと前のことです。インテルの社内の誰かが、クリステンセン教授が書いたハードディスクドライブ業界についての学術論文を読み、グローブにクリステンセン教授に会うよう進言したのがきっかけでした。クリステンセン教授の役割はグローブにインテルがどのように凋落していくかを説明するというものでした。
「10分やろう。インテルについてどう思うか説明してくれ」
グローブは野心あふれる半導体エンジニアらしく、ぶっきらぼうに言いました。
「学者が書いたつまらんものを読む時間がないんだ」
何をすべきかではなく、どのように考えるか
クリステンセン教授は半導体について何も知りませんでした。しかも相手はインテルCEOのグローブです。そこで彼は次に何をすべきかを語るのではなく、別の業界を事例を使ってわかりやすく説明しましょう、と言いました。
彼が選んだのは鉄鋼業界です。電炉メーカーは高炉メーカーよりも鉄筋を安く製造する技術で頭角を現しました。高炉メーカーは低マージンで低品質の製品を自分たちはもうつくらなくてよくなったと歓迎しました。その後、電炉メーカーはみるみる力をつけ、高炉メーカーの市場を奪いました。
クリステンセン教授がそこまで話すと、「もういい」とグローブが話を中断しました。
「クリステンセン教授、つまりインテルの敵はAMDということか。新しい部門を設立し、ローエンドの製品を投入する必要があるな」
そこから比較的廉価なパソコン向けのCPU、Celeronが開発されました。Celeronは同社の歴史の中で最も生産量の多い製品となりました。
「わたしはアンディに何をすべきかを伝える立場ではありませんでした。その点についてはわたしから言うことはなかった」とクリステンセン教授は言いました。
「でもわたしには理論がありました。わたしの理論を通じてわかってもらいたいことがありました。……わたしはアンディに何をすべきかではなく、どのように考えるかを教えたのです」
1997年、グローブは、ラスベガスで開催されたCOMDEXの大勢の聴衆の前で『イノベーションのジレンマ』の本を掲げ、これは自分がここ10年間に読んだ「最も重要な本」と言いました。同じ年、グローブは経営学アカデミーの年次会議で基調講演を行いました。これは、学者だけが熱心に参加する学術会議のようなものです。
彼はここでもクリステンセン教授の本を持ち出し、「失礼な言い方かもしれないが、学者の書いた本で役に立つと思った本はない。この本以外は」という趣旨のことを言いました。
聴衆の教授たちは、ひきつったような笑いを浮かべたあと、顔を曇らせたことでしょう。クリステンセン教授の論文は一流の学術雑誌に一度も掲載されたことはありませんでした。それは周知の事実でしたが、クリステンセン教授はそのことを恥じてはいませんでした。
一方、クリステンセン教授の論文は、アマゾンのジェフ・ベゾスCEOが人に勧めるほど気に入り、アップルのCEOだったスティーブ・ジョブズに深い影響を与え、インテルを破滅から救いました。その論文はハーバード・ビジネス・レビューがこれまでに発行した中で最もダウンロードされた論文となりました。
クリステンセン教授はその時代の最も影響力のある経営思想家とされ、世界に新しい見方を与えました。それでも著名な学術雑誌にクリステンセン教授の論文が掲載されることはありませんでした。
アカデミズムから距離をとった経営学者はクリステンセン教授だけではありません。競争戦略のマイケル・ポーター、ブルーオーシャン戦略のチャン・キム、チェンジ・マスターのロザベス・カンター、そして最近ではビジネスモデル・カンバスのアレックス・オスターワルダーらも、論文を一流学術誌に発表することはほとんどありません。
一方で、アカデミズムの外では、企業のマネジャーレベルで『Administrative Science Quarterly』『Strategic Management Journal』『Academy of Management Review』といった学術雑誌の名前を知っている人はほとんどいないでしょう。医学、法律、および工学の分野では見られないこの断絶には、多くの原因があります。
その理由が何であれ、つまりはこういうことです――賢い人たちは誰も興味がないような質問に答えるために人生の時間を費やし、そうやって得られた自分の洞察を書いたとしても誰もそれを読まない。
少し前まで中西部の有名なビジネススクールの終身教授であった友人が、転職を考えていました。彼は50代前半で、論文を何本も重要な学術誌に発表し、潤沢な寄付金で運営されている研究所で安全かつ快適に過ごしていました。彼は学部長と会い、これから何をしようかという話をしました。学部長は言いました。
「もっと趣味を楽しんだらどうだ? 君の目の前には輝かしい10年がある。過去を振り返るべきではない。美しい夕日に向かって航海するんだよ」
過去を振り返るべきではないのは、おそらく、わたしたちの多くが、本当にやりたくないことをしているか、本当に重要なことを怠っているからです。クリステンセン教授はいつも過去を振り返り、さらによいものを得るために、何かを捨てることを恐れませんでした。
彼の人生には優先順位がありました。彼は、白血病の治療で車椅子の生活になるまで、最愛のMBAクラスを教え続けました。クリステンセン教授は授業を代理に任せるようになっても、教室にいさせてほしいと学部長に願い出ました。できる限りの方法で議論に貢献したかったのです。
博多はつ花のボランティア修理担当が社長のブログをお借りして、発言させていただきました。
接待用高級お弁当の博多 はつ花 の商品はちょっと高級な、無農薬、無人工甘味料、無添加物を食材に使っています。配送には、冷凍車を用いております。お渡し後は、早めにお召し上がりのほど、お願い申し上げます。
ランチタイム、歓送迎会のお弁当のご予約、受付中。ご予約日は翌日以降でございます。
クレイトン・クリステンセン教授は、ハーバード・ビジネス・スクールの博士課程のあるセミナーで学生たちに問いかけました。クラスにはビジネススクールの教授を目指す数十人の新入生がいました。当時のクラス生徒は世間知らずで、実際のビジネスについてはほとんど何もわかっていませんでした。
「わたしが知りたいのは、無敵だと思われていた企業のほとんどが、10年から20年後には、業界の中位または下位に転落するのはなぜなのか、ということです。わたしは大企業のCEOを何人も知っていますが、彼らの聡明さは衰えを知りません。企業の業績が絶好調である間は彼らの知性が称賛されますが、業績が悪化すると愚かさを批判されます。しかし、わたしは人間の知性の振れ幅がそれほど大きいとは思えないのです」
「そこで問うべきは……」
クリステンセン教授は黒板を見つめ、チョークを拾い上げて続けました。
「それほど聡明な人でさえ、成功し続けるのが難しいのはなぜなのか?」
これこそがまさに「イノベーションのジレンマ」でした。つまり、「正しく行う」ことが失敗を招くのです。
クリステンセン教授の『イノベーションのジレンマ』が出版されたのは1997年。それから20年以上が経過した、今でも多くの大企業は「正しく行う」ことに躍起になっています。
顧客の声に耳を傾け、より多くのより良い製品を提供するために、新しいテクノロジーに積極的に投資し、慎重に市場動向を分析し、最良のリターンが得られそうなイノベーションに計画的に出資する――皮肉なことに、これらすべてを正しく行っているがゆえに、優良企業はディスラプション(破壊)をもたらす新興企業にとって代わられるのです。
クリステンセン教授の時代、こうした転落を経験した企業に、ソニーに負けたRCA(RCAレコード)がありました。DEC(ディジタル・イクイップメント・コーポレーション)に苦しめられたNCRがありました。サンディスクに苦しめられたシーゲート・テクノロジーがありました。さらに、ホンダと戦ったハーレーダビッドソンも。
現在このパターンは、アマゾン対ウォルマート、ハリーズ対ジレット、テスラ対BMW、リボルート対HSBC、およびベターメント対メリルリンチなどと置き換えられます。役者は入れ替わりつつ、同じ物語が続いているのです。
RCAがソニーにやられた物語を振り返ってみましょう。

RCAがトランジスタ技術をはじめて発見したとき、同社はすでに真空管のカラーテレビで大成功していました。同社はトランジスタをちょっと面白い新技術というくらいの認識で実用化は考えず、ソニーというほとんど無名の日本企業にこの技術のライセンスを供与しました。
ソニーはすぐにはトランジスタテレビを作ることはできませんでしたが、世界初のトランジスタラジオを製造することに成功しました。音質は酷いものでしたが、ティーンエイジャーたちは親にがみがみ言われることなくロックを自由に聴くことができるとこのラジオに熱狂しました。そこからトランジスタラジオは広まっていきました。しかし利益率が非常に低かったので、RCAはこの技術にさらに投資する理由がありませんでした。RCAは研究開発費のすべてを稼ぎ頭の真空管カラーテレビの改善のために投入したのです。
一方、ソニーはトランジスタ技術を使った次の大ヒット商品を探していました。そして、低所得層向けに格安のポータブル白黒テレビを発売しました。Tummy Televisionと呼ばれるこのテレビは、お腹の上にのるほど小さいもので、これは中産階級のリビングルーム向けに設計されたRCAの大型テレビの向こうを張ったものでした。当時、RCAがトランジスタ技術に投資して、性能も低いテレビをそれほど魅力的のない市場に投入するなど考えられないことでした。
ソニーは一歩一歩着実にトランジスタの性能を改善していき、世界初のオールトランジスタカラーテレビを発売しました。自分たちが開発した技術をライセンス供与してから30年がたっていました。下級技術と思われていたものが後にとてつもなく有用性が高いものになったわけです。クリステンセン教授はこれをディスラプティブ(破壊的)な技術と呼びました。その後、この言葉はビジネス用語として定着し、シリコンバレーのスタートアップの間で合言葉となりました。
クリステンセン教授は自分の理論を掘り下げるために多くのケースブックを書きました。業界の未来を予測し、医療、幼稚園から高校までの教育、そして高等教育の調査などを行いました。彼は国家の繁栄の原因を分析し、最終的に生命とその意味までも研究対象としました。
彼は経営陣がよい判断ができるようにと彼の理論を実践するためのコンサルティング会社Innosightを設立しました。ハーバード・ビジネス・スクールで最も人気のあるMBAのクラスを教えながら、彼はベンチャー企業に種をまき、ディスラプティブな可能性のあるスタートアップに投資しました。
クリステンセン教授の別の授業で、彼がインテルのCEOだったアンディ・グローブと最初に会った時の話も聴きました。彼らの邂逅は、『イノベーションのジレンマ』が出版されるずっと前のことです。インテルの社内の誰かが、クリステンセン教授が書いたハードディスクドライブ業界についての学術論文を読み、グローブにクリステンセン教授に会うよう進言したのがきっかけでした。クリステンセン教授の役割はグローブにインテルがどのように凋落していくかを説明するというものでした。
「10分やろう。インテルについてどう思うか説明してくれ」
グローブは野心あふれる半導体エンジニアらしく、ぶっきらぼうに言いました。
「学者が書いたつまらんものを読む時間がないんだ」
何をすべきかではなく、どのように考えるか
クリステンセン教授は半導体について何も知りませんでした。しかも相手はインテルCEOのグローブです。そこで彼は次に何をすべきかを語るのではなく、別の業界を事例を使ってわかりやすく説明しましょう、と言いました。
彼が選んだのは鉄鋼業界です。電炉メーカーは高炉メーカーよりも鉄筋を安く製造する技術で頭角を現しました。高炉メーカーは低マージンで低品質の製品を自分たちはもうつくらなくてよくなったと歓迎しました。その後、電炉メーカーはみるみる力をつけ、高炉メーカーの市場を奪いました。
クリステンセン教授がそこまで話すと、「もういい」とグローブが話を中断しました。
「クリステンセン教授、つまりインテルの敵はAMDということか。新しい部門を設立し、ローエンドの製品を投入する必要があるな」
そこから比較的廉価なパソコン向けのCPU、Celeronが開発されました。Celeronは同社の歴史の中で最も生産量の多い製品となりました。
「わたしはアンディに何をすべきかを伝える立場ではありませんでした。その点についてはわたしから言うことはなかった」とクリステンセン教授は言いました。
「でもわたしには理論がありました。わたしの理論を通じてわかってもらいたいことがありました。……わたしはアンディに何をすべきかではなく、どのように考えるかを教えたのです」
1997年、グローブは、ラスベガスで開催されたCOMDEXの大勢の聴衆の前で『イノベーションのジレンマ』の本を掲げ、これは自分がここ10年間に読んだ「最も重要な本」と言いました。同じ年、グローブは経営学アカデミーの年次会議で基調講演を行いました。これは、学者だけが熱心に参加する学術会議のようなものです。
彼はここでもクリステンセン教授の本を持ち出し、「失礼な言い方かもしれないが、学者の書いた本で役に立つと思った本はない。この本以外は」という趣旨のことを言いました。
聴衆の教授たちは、ひきつったような笑いを浮かべたあと、顔を曇らせたことでしょう。クリステンセン教授の論文は一流の学術雑誌に一度も掲載されたことはありませんでした。それは周知の事実でしたが、クリステンセン教授はそのことを恥じてはいませんでした。
一方、クリステンセン教授の論文は、アマゾンのジェフ・ベゾスCEOが人に勧めるほど気に入り、アップルのCEOだったスティーブ・ジョブズに深い影響を与え、インテルを破滅から救いました。その論文はハーバード・ビジネス・レビューがこれまでに発行した中で最もダウンロードされた論文となりました。
クリステンセン教授はその時代の最も影響力のある経営思想家とされ、世界に新しい見方を与えました。それでも著名な学術雑誌にクリステンセン教授の論文が掲載されることはありませんでした。
アカデミズムから距離をとった経営学者はクリステンセン教授だけではありません。競争戦略のマイケル・ポーター、ブルーオーシャン戦略のチャン・キム、チェンジ・マスターのロザベス・カンター、そして最近ではビジネスモデル・カンバスのアレックス・オスターワルダーらも、論文を一流学術誌に発表することはほとんどありません。
一方で、アカデミズムの外では、企業のマネジャーレベルで『Administrative Science Quarterly』『Strategic Management Journal』『Academy of Management Review』といった学術雑誌の名前を知っている人はほとんどいないでしょう。医学、法律、および工学の分野では見られないこの断絶には、多くの原因があります。
その理由が何であれ、つまりはこういうことです――賢い人たちは誰も興味がないような質問に答えるために人生の時間を費やし、そうやって得られた自分の洞察を書いたとしても誰もそれを読まない。
少し前まで中西部の有名なビジネススクールの終身教授であった友人が、転職を考えていました。彼は50代前半で、論文を何本も重要な学術誌に発表し、潤沢な寄付金で運営されている研究所で安全かつ快適に過ごしていました。彼は学部長と会い、これから何をしようかという話をしました。学部長は言いました。
「もっと趣味を楽しんだらどうだ? 君の目の前には輝かしい10年がある。過去を振り返るべきではない。美しい夕日に向かって航海するんだよ」
過去を振り返るべきではないのは、おそらく、わたしたちの多くが、本当にやりたくないことをしているか、本当に重要なことを怠っているからです。クリステンセン教授はいつも過去を振り返り、さらによいものを得るために、何かを捨てることを恐れませんでした。
彼の人生には優先順位がありました。彼は、白血病の治療で車椅子の生活になるまで、最愛のMBAクラスを教え続けました。クリステンセン教授は授業を代理に任せるようになっても、教室にいさせてほしいと学部長に願い出ました。できる限りの方法で議論に貢献したかったのです。
博多はつ花のボランティア修理担当が社長のブログをお借りして、発言させていただきました。
接待用高級お弁当の博多 はつ花 の商品はちょっと高級な、無農薬、無人工甘味料、無添加物を食材に使っています。配送には、冷凍車を用いております。お渡し後は、早めにお召し上がりのほど、お願い申し上げます。
ランチタイム、歓送迎会のお弁当のご予約、受付中。ご予約日は翌日以降でございます。
 完全予約制高級仕出し弁当専門店
完全予約制高級仕出し弁当専門店
弊社のお弁当は、大切な方と一緒に頂くプレゼント用のお弁当です。上棟式、法事、喜寿、米寿、白寿、敬老会、大相撲九州場所、博多座観劇、セミナー、ブランド品ご商談会などでお使い頂いております。
 完全予約制高級仕出し弁当専門店
完全予約制高級仕出し弁当専門店弊社のお弁当は、大切な方と一緒に頂くプレゼント用のお弁当です。上棟式、法事、喜寿、米寿、白寿、敬老会、大相撲九州場所、博多座観劇、セミナー、ブランド品ご商談会などでお使い頂いております。
Any comments are welcome. Your comments are displayed after permission.